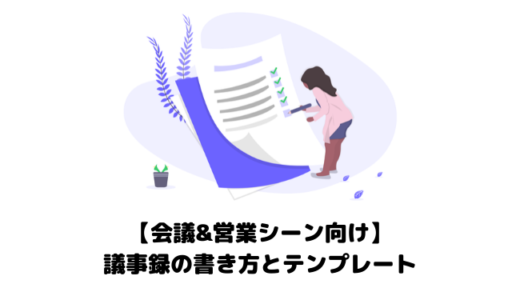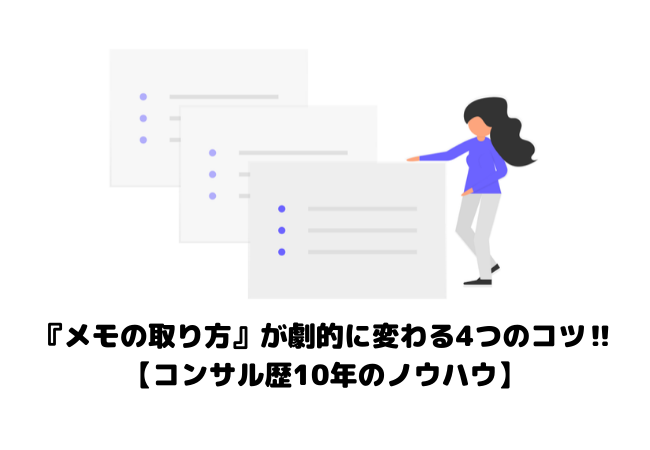
 ゆーろ
ゆーろこの記事を書いている僕は30代で、現役戦略コンサルタントとして10年働いています。
当ブログ『ビジネスギーク』で転職情報や年収を上げる方法を発信しています
:https://twitter.com/yuro_tasteearth
本記事では『メモの取り方』が劇的に変わる4つのコツ‼について紹介していきます。
 でんさん
でんさん・メモの取り方が下手な理由が知りたい
・メモを取るコツが知りたい!
本記事はこんな方の悩みを解決する記事です。
なぜなら僕自身が本記事で紹介しているメモの取り方でコンサルタントとして10年生きてきたからです。
本記事を読めば必ず『メモの取り方』のコツをマスターできます。
 ゆーろ
ゆーろメモは備忘録になることもさることながら、積極的に活用すればアイデア出しや、プレゼン資料・企画書・報告書のシーンでも活用できます。
そしてなによりメモの一番の役割は、仕事で成果に役立つことです。メモの取り方と仕事の成果は直結します。
メモを上手に取れて成果が出ていない人はいましたが、成果を出している人でメモを取れない人は一人もいません。
本記事の『メモを取るコツ』を実践して、メモの取り方を理解し現場で活用できるようにしていきましょう!
参考記事:【圧倒的に作業効率化を実現】コンサルタントが使うビジネスグッズ21選
1.メモの取り方を学ぶ6つの効果
メモの取り方を学ぶどんなメリットや効果があるかを書いていこうと思います。
メモの効果を認識しておくとメモの取り方を腰を据えて学ぶようになります。
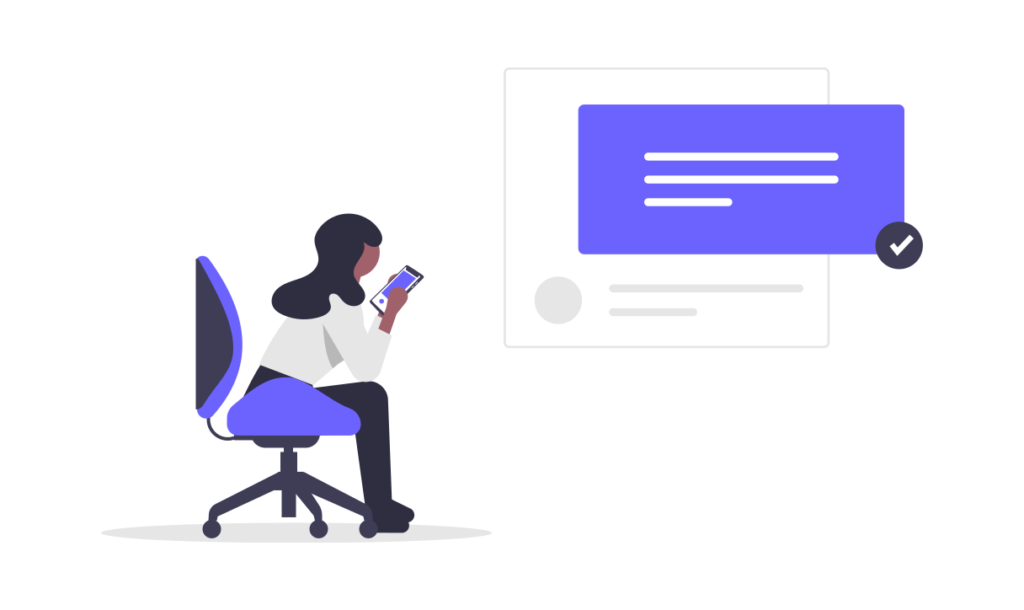
1.1.メモの取り方を学ぶ効果①:備忘録になる
メモの効果の一つ目は備忘録として活用できることです。
なぜなら過去に聞いた話はもちろん、自分の頭に浮かんだ考えやアイデアを即座にメモすることで、備忘録になるからです。
活字は常にメモに残っているので、メモを見返せばいつでも当時の内容や気づきを思い出すことができます。
具体的に僕は仕事もプライベートも必ずメモを持ち歩いて、タスクや気付いたことはすぐにメモしておくようにしました。
 ゆーろ
ゆーろ1.2.メモの取り方を学ぶ効果②:考えをまとめることができる
次に、メモを取ることでバラバラに散らばった情報をまとめるのに役立ちます。
理由は情報さえ残っていれば、情報を全て棚卸して振り分け、内容を整理できるからです。
具体的に、以下のシーンでのメモはその日のうちにまとめるようにします。
- 営業訪問時・上司とのMTGやアドバイス
- 会議
- セミナー・勉強会など
- プライベート
記憶が新しい内に内容をまとめると、記憶の定着につながり、学びを確実なものにできます。
僕の場合、営業訪問に毎日2-3件行くので、メモはその日のうちにまとめます。自分の成長に関するメモは、振り返りもかねて週末にまとめています。
記憶は新鮮なうちにまとめるほど、効果が高まるので、忙しい人でも週末までには1週間のメモをまとめるようにしましょう。
 でんさん
でんさん1.3.メモの取り方を学ぶ効果③アイデアを生み出せる
メモを取ることでアイデアを生み出すことができます。
なぜならアイデアの元となる情報を、自分の手元に保管しておくことができるからです。
具体的にはメモから以下のように思考を巡らせます。
- どのようにメモの情報を活かせるか
- 現場で新しく使えるテクニックはないか
メモから自分がどのように考え、活かせるかを考える過程が最も重要です。
- 「読書について」の著書で、読書の第一人者であるショーペンハウアーは、読書の本来の目的を「考える」ことだと述べています。
- メモ本来の目的も「考えること」にあります。常にアウトプットに活かすためのメモを取りましょう。
1.4.メモの取り方を学ぶ効果④:感性が高まり、成長スピードが一気に上がる
整理したメモからアウトプットを繰り返すようになると、メモが習慣化し、感性が高まるようになります。
なぜならメモを取るようになると「目の前の些細なできごと」や「成長のための学び」に気づけるからです。
見逃しがちな些細なでき事や、学びの種に気付くことができるようになると、情報に敏感になり収集した情報を学びに繋げることができます。
更には、気づいたことを実践・改善することで成長スピードが一気に上がります。
1.5.メモの取り方を学ぶ効果⑤:仕事の成果が出る
メモを上手に取れるようになると、仕事の成果も出ます。理由は相手の話をきちんと理解できるからです。
メモを取れるようになると、相手の話や課題も正確に理解出来るようになります。そして課題に対して適切なソリューションを提供することができます。
お客様が営業マンに最も求めている要素は「自分のことを理解してくれること」だそうです。
お客様は営業力や質問力や提案力でなく、自分のことを理解してくれる営業マンを求めるのです。
詳しくは無敗営業で解説しています。
お客様の課題を正確に把握できるようになると、課題に対して適切な解決法を考えて提供すればよいだけなので自然に成果も出てきます。
それくらい、お客様の話を正確に理解できることは重要なスキルになるため、徹底的にメモ力を高めましょう。
 ゆーろ
ゆーろ多くの営業マンは関係構築や営業トークに磨きをかけますが、まず第一にきちんとメモと取れることが、仕事で成果を上げるうえでの重要な観点だと覚えておきましょう。
1.6.メモの取り方を学ぶ効果⑥:周囲からの信頼が生まれる
メモの取り方を学ぶと周囲からの信頼が生まれます。
なぜならメモが取れるようになると、仕事の抜け漏れもなくなり、マルチタスクもできるようになるからです。
会議の論点なども正しく整理できるようになり、仕事の成果も上がるため、周囲から信頼されるようになります。
上司はあなたの仕事にホームランを期待しているわけではなく、チームのために言われたことを言われた通りこなす正確さを求めています。
与えられたタスクをきちんとこなすことができるようになれば、おのずと次から次へと仕事の依頼が来ます。
更に成果を上げて昇給・昇進も可能ですし、難しい仕事も引き受けることができるので自分のレベルもどんどん上がってきます。
このように、メモが取れる効果は大きく、メリットばかりなのです。
 ゆーろ
ゆーろ2.メモの取り方が下手な5つの理由
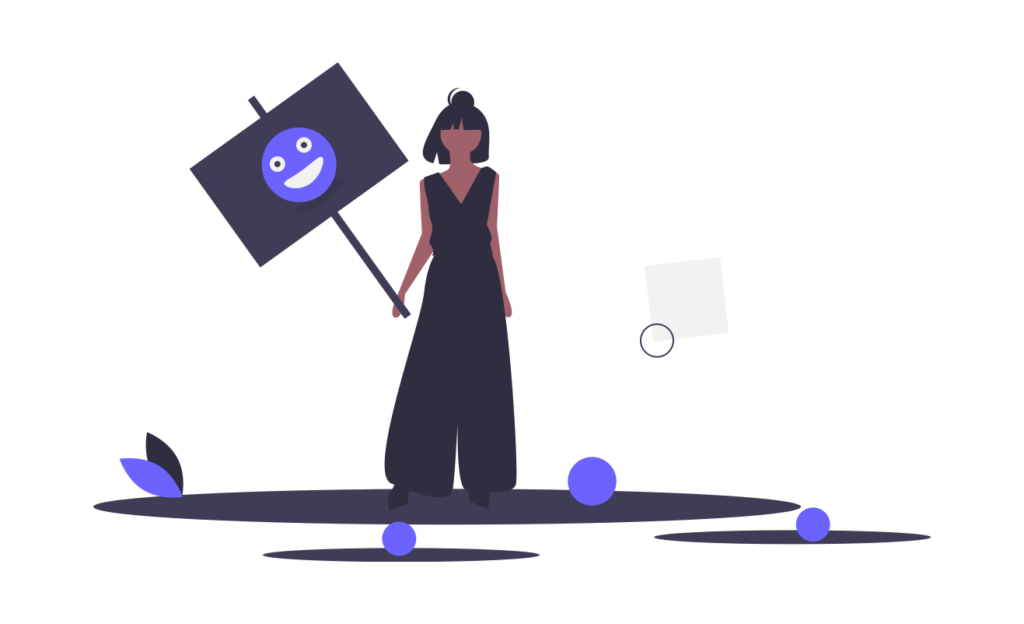
次に、メモの取り方が重要なことに気付いていながら、メモの取り方が下手な理由について書きます。メモが取れないのには明確な理由があります。
具体的には、大きく4つの理由があります。順に説明していきます。
- 文頭にテーマを書いていない
- 1ページに複数のテーマを書きすぎる
- 聞いた内容を全て丸写しする
- 余白がない
僕の場合、自分がメモの取り方が下手な理由を認識し始めたあたりから、変化が現れるようになりました。
メモの取り方が下手だと自身で思っている人は、まず自分自身を客観的に見つめて、原因を把握することから始めましょう。
2.1.文頭に「テーマ:何の話か」を書いてない
文頭に「テーマ」を書い
なぜなら、人は「何の話をしているか書いていないと脳に情報を入れることができない」からです。
ポイントは書き始める時は、メモの一番上に「〇〇について~」と記載することです。
例えば営業会議を行っていて、学ぶべきポイントがあったときは以下のように文頭に記載します。
メモ帳の使い方
■優れた営業マンの要素について
- 厚かましく自分から営業をかけない
- 聞くが9割、話すが1割
- 毎回事前に話す内容を準備している
上記のように記載することで「優れた営業マンについてのメモを取っている」と脳で意識することができます。
更にはメモを見返すときに、「優れた営業マンの要素についてのメモだったな」と自分が書いたメモを振り返る時に思い出せます。
スキーマ学習法について学ぶとより文頭にテーマを書く重要性が理解できるはずです。
2.2.1ページに複数のテーマを書きすぎ
メモが下手な人の特徴に1ページに複数の議題についてメモする癖があります。
理由は1ページにいくつも議題を書きすぎると、メモ取る時に集中力が分散してしまうからです。
話を聞いているうちに、何の話をしているのかわからなくなり局話が理解できなくなってしまいます。
また振り返る時も、複数の議題・テーマが記載されていると、何の話をしていたか思いだすのに時間がかかるので避けましょう。
メモ帳の使い方は、1テーマにつき1ページ使うのが最もメモの使い方としては効果的です。
 でんさん
でんさん現在なんの話をしているか、どの部分を話しているか分からなくなると、正確にメモが取れなくなってしまいますので、議題ごとにページを変えるようにしましょう。
2.3.聞いた内容全てを丸写しする
自分自身もそうでしたが、メモが取れない人ほど聞いた話を丸写ししようとします。
なぜなら話を聞き洩らしたくないため、話を一言一句見逃さずにメモしようとするからです。これが一番メモが上達しない理由です。
しかし結果的に不要な部分もメモを取ろうとして、時間が足りず本当に重要な部分を聞き逃してしまうことがあるので、丸写しは絶対にやめましょう。
丸写しする人のほとんどが、話の議題を体系的に理解できていません。
また、話の全体像が理解できないため、別の話に変わったときに理解できなかったり、話に追いつけなくなってしまいます。
 ゆーろ
ゆーろしかしそれでは一向にメモの取り方をマスターできないので、最初に議題・テーマを書き、その後は論点や要点を書いてから具体例を書くようにしましょう。
2.5.メモ帳が小さすぎる
メモ帳が小さすぎる人も議事録が下手な傾向にあります。なぜならメモ帳が小さいと会話の全体像を捉え切れないからです。
具体的には小さいメモ帳にほぼ丸暗記のメモを取って、次から次へとページを変える人です。
これでは絶対話の全体像を理解できないので、できればA4かA3サイズの方眼用紙(個人的には横書き)を使うようにしましょう。
方眼用紙を使うことで、話を体系的に理解でき、話を集中して聞くことができるためおすすめです
安いノートでも構いませんし、いろいろ試してみましたが僕はニーモシネの方眼用紙を愛用しています。
※モレスキンほど高級ではないが最高の書き心地と、ハードカバーでカバンに入れても紙がおれず、ノートの保存も完璧にできます
2.5.余白がない
メモが上手く取れない人ほど、メモ帳に余白がありません。
なぜなら余白がないと、補足や自分の感想を書きたくても場所がなく、自由なアイデアを思いつけません。
また余白が無ければ、メモをパッと見た時に理解しにくく、情報を探す際も大変です。またメモした情報をまとめる時も苦労します。
ノートは日々進化させていくものであり、数か月・通年後にメモを見返した時にメッセージを書き込んだりするとよいのですが、余白がないと、新しいコメントもできません。
3.メモの取り方~4つの基本・準備編~
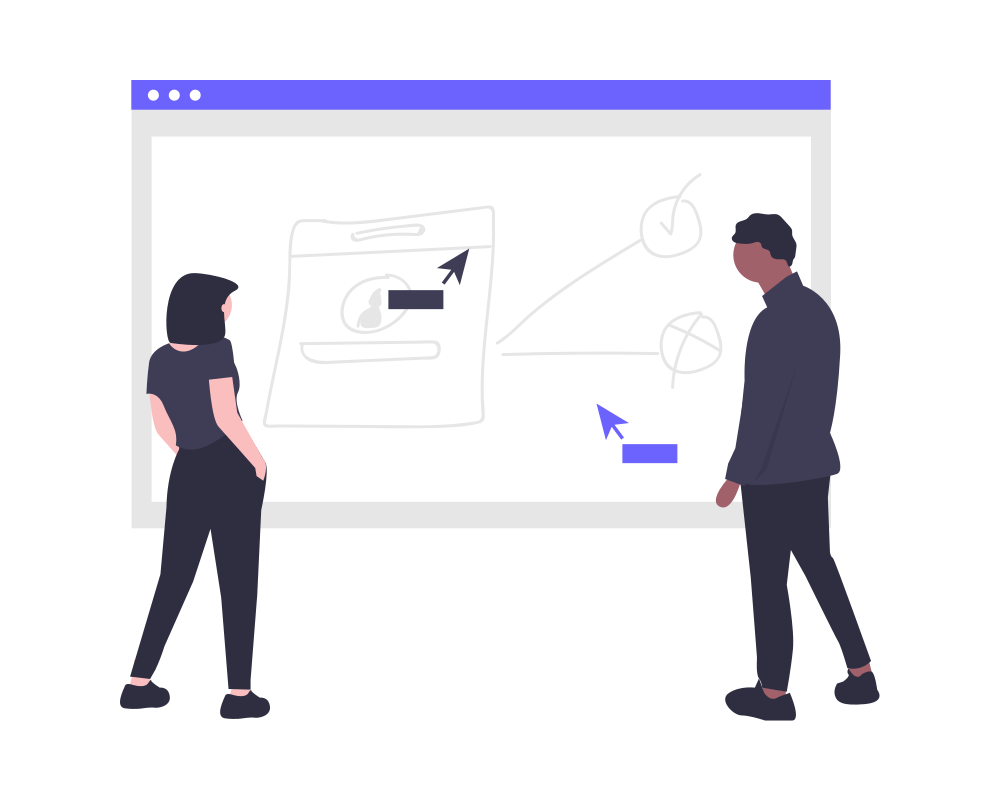
ここまで、メモの効果とメモが上手く取れない人の特徴について説明していきました。
次からメモの取り方の基本についてお伝えしていきます。
メモの取り方の基本を正しく押さえることで、これまで我流でメモを取っていた方からすると大きな改善が図れるはずです。
3.1.日付・議題内容を事前に書いておく
メモを取る時は事前の準備が重要です。
営業訪問・会議・プレゼンやセミナーに参加する前には、必ず事前に日付や議題を書いておきましょう。
なぜなら会話は急に始まる場合があるので、会話が始まってから議題やテーマを書くと会話を聞き逃したり、自分のペースでメモを取ることが難しくなりからです。
事前に議題についてわからない場合は、仮で構いませんので予測される議題を書いておきましょう。
大体の場合、事前にどんな会話が行われるかは予想がつくため議題を書くことは難しくないはずです。
3.2.はじめに「何の話をしているか」をメモする
会話が始まったら、常に何の話をしているのか(~について)を意識するようにしましょう。
- 今月の売上について話している
- 営業改善に向けた戦略の話をしている
- お客様が東南アジアに商品展開についての話をしている
と、常に議題について聞き漏らさないことが重要です。
議題を聞き逃さなければ、話がそれた場合も「今は今月の売上の話をしてたな」と、議題に戻ってくることができます。
 でんさん
でんさんつねに『今何の話をしているか』を念頭に置いて話を聞くんだぞ
3.3.議題から話が逸れてないか常に確認する
話を聞くときは「議題から話が逸れてないか」常に確認しましょう。
なぜなら会話が進んでいくと、いつの間にか議題が変わっていることはよくあるからです。
会話中は全員が紙を持って話しているわけではないので、論点のずれた話をする人が何人かあらわれます。
常に頭の中で「今は今月の売上の話をしてるんだよな」となんの話について話していたかを思い出します。
例えば、急に部長が「来月の売上は大丈夫なんだろうな!?」と話したとします。
そんな時は「今は今月の売上をしているのに、来月の話になっちゃったよ」と議題が変わっていることに気付き、別ページに「来月の売上について」と議題を書くようにしましょう。
このように対応していくことで、理解がずれることなく、相手の論点がずれたことにも気づけます。
3.4.議題が変わったらページも変える
議題が変わったら、メモを取っているページを変えましょう。
議題が変わっているにもかかわらず、同じページにメモを取っていると会話の論点がずれているため、話が理解ができなくなります。
あなたはメモの練習をして「なんの話をしているか」理解できるようになっているので、仮に議題が変わっても察知することができるはずです。
 よめちゃん
よめちゃん4.メモを取るならPCの方が圧倒的におすすめ

よく、メモを効率よく取るには手書きとPCどっちがいいんですか?と質問を受けます。
結論、自分の書きやすい方がいいと思いますが、個人的な意見としては、パソコンを圧倒的におすすめします。理由は以下の通りです。
PCのメモがおすすめな理由
- 書くよりもタイピング速度が圧倒的に早い
- 新しい議題になった時にすぐ別の場所に打ち込める
- ページをめくらなくて済むため、議題が変わったときに気付きやすい
- 消す作業が簡単
- 議論後、メモを即座にまとめられて便利
- メモの一元管理が可能
どうしても手書きが良い人は、手書きでいいと思います。正解はないので自分が良いと思う方でメモを取れば大丈夫です。
例えば営業現場の場合、目の前でパソコンを売っていると相手からの印象が悪い場合もあります。
その他にもPCを持っていくのは不便な場所は小さなメモを持っていく方がおすすめです。※携帯でメモを取ることも可能です。
ちなみに近年は手書きでメモを取る会社は減ってきており、楽天に訪問に行ったときは余裕でみんなPCでメモを取っていました。
僕自身も、これまで数千件の訪問に行きましたが、PCでメモを取っていて怒られたことは一度もありませんでした。
大切なのはPCを打ちながらでも相手の目を見て会話をしていくことではないでしょうか?
いずれにしても、議論内容が正確にメモできていること、アウトプットに活用できる目的を果たしていれば何でもよいと思います。
5.メモの取り方『練習法』4つ

最後にメモの取り方の練習法7つについてお伝えしていきます。メモ取り方を練習することで、より楽に正確に楽にメモを取ることができます。
メモが取れると人生が変わります。ビジネスが本当にイージーになるので最初はつらくてもあきらめずに頑張ってください。
5.1.メモの取り方練習①:5W2Hを明確にする
メモの取り方の練習の1つ目は『5W2Hを意識しながらメモを取る』ことです。
なぜなら基本的にビジネス会話は会話は基本的に5W2Hで構成されているからです。具体的には以下の順番で確認していきます。
- Who:誰が
- When:いつ
- Where:どこで
- What:何を
- Why:何のために
- How:どのように
- How much:いくらで
主語と会話の方向を理解して「いつ・どこで・何を・何のために・どのように・いくら」に関する情報をメモすると抜け漏れが減ります。
5.2.メモの取り方練習②:図解思考を取り入れる
新たに練習するときは丸暗記やベタ打ちはもう卒業しましょう。その代わりに図解思考と取り入れます。
断言しますが、メモで丸暗記やベタ打ちをしてもメモ力は向上しません。なぜなら、自分の頭に体系的に(頭に入りやすいように)情報が入らないからです。
図解思考を習得して、上方の粒度の大きな順にメモを取っていくことで、頭にわかりやすく入ります。
本章についてメモを取るとすると以下のようになります。
■メモの取り方の練習法について
①5W2Hを明確にする
*以下7つを意識してメモを取る
- Who:誰が
- When:いつ
- Where:どこで
- What:何を
- Why:何のために
- How:どのように
- How much:いくらで
上記のように、階層別で情報収集すると、メモが頭にわかりやすく入るようになります。
詳しくは『議事録の書き方』をプロ取材者が超わかりやすく解説‼でわかりやすく紹介しています。
5.3.メモの取り方練習法③:メモを取った日に学びをまとめる
多くの人は、メモをと取ることに重きを置きますが、もっと重要なのは学びを振り返りながらまとめることです。
学びを振り返ることで、自分の考えを整理して頭の中に収納できるからです。
情報を整理する過程で情報をまとめる能力がつき、整理した情報を入れることでのちに情報を取り出したい時にスムーズに対応することができるようになります。
僕も現職は調査の会社でメモを取る毎日ですが、まず最初に教えてもらったのが「メモや議事録はその日のうちにまとめる」ことでした。
聞いた話をその日のうちにまとめることで記憶の整理と定着に役立ちます。
忙しすぎて当日にメモをまとめることができない場合は、必ず週末に情報をまとめてください。
週末を超えるとほぼメモをまとめ返さなかったり、忘れてしまっていることが多く、学びの鮮度が落ちてしまいます。
料理と同じで新鮮な情報はその日のうちに調理するようにしましょう。
5.4.メモの取り方練習法④:自分の考え(示唆)も書く
最後に、メモをまとめる時は必ず自分の考えを書くようにしましょう。
- 他人の話を聞いて賛成か反対か、そう思う理由は何か?
- お客様の課題に対して、自分だったらどのように解決するか?
- 課題に対して提供できる自社の商品はあるか
- 情報をまとめると、最終的に言えることは何か?
最終的に、情報から導き出せる自分の考えや答えを「示唆」と呼び、コンサルティング業界ではこの示唆をとても大切にしています。
どれだけ情報収集ができても、情報から何が言えるか自分の考えや意見がないと社会やお客様から評価されないので注意しましょう。
逆に、自分の考えや考えを裏付ける証拠がしっかりしていれば、相手が部長だろうが社長だろうが必ず価値を提供できますので、自信をもってアドバイスや意見を伝えるようにしましょう。
6.メモの取り方を効率化する工夫
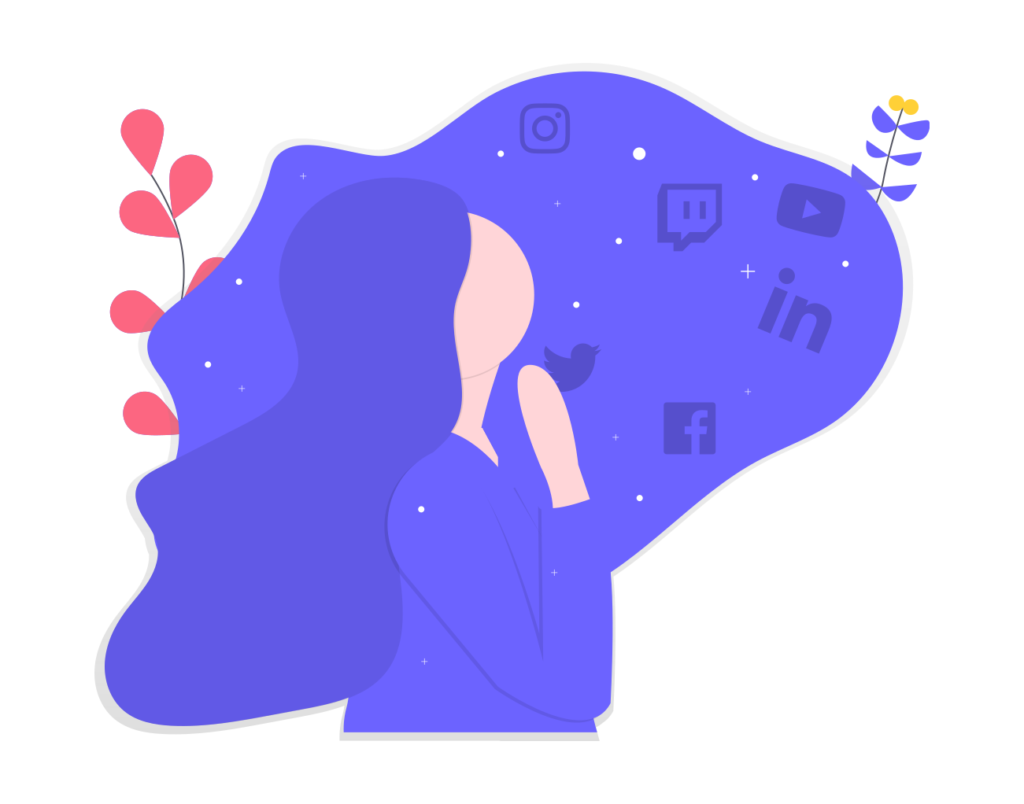
6.1.メモ効率化の工夫①:いつでも取り出せるサイズのメモ帳を持っておく
練習で使うならメモ帳はいつでも取り出せるサイズのメモ帳を選びましょう。
メモしたい情報が飛び込んできたときに、さっと取り出せなければメモの意味がないからです。
大きさはポケットサイズの物か、いつもかばんを持ち歩くようであればカバンからすぐ取り出せるサイズの物がおすすめです。
材質や特徴はロールできるものが便利ですが、外側が弱いとページが剥がれるため、おすすめしません。
ここでも一番おすすめなのはニーモシネのメモ帳です。
外側はハードカバーで中は方眼紙になっています。上質なブラックな雰囲気なので、どこにもっていっても大丈夫です。
6.2.メモ効率化の工夫②:メモ帳は上質なものがおすすめ
会議や営業現場に訪問する場合、お客様の前に広げるため、上質なメモ帳を好む人は、ハードカバーかつ何年経っても廃れない保存が効く「上質なメモ帳」を持つことをおすすめします。
上質なメモ帳を持つことで、メモ帳自体を大切に使用・保管するようになりますし、大切な情報のみを書き込む癖もつきます。
おすすめはやはりモレスキンでで、僕のとてもお世話になりましたが、ハードカバーメモ帳は何年たっても同じ品質のまま保管が可能です。
また、RODHIA(ロディア)のメモ帳も上質で、カバーが手になじみやすく、方眼シリーズが多いのでおすすめです。
モレスキンと違い、ページがちぎりやすいので、1日の学びをまとめて不要なものは捨てて、次の日からまたきれいなメモ帳を使えます。
僕も学生時代からロディアには大変お世話になりました。いいメモ帳を使ってより良い自分になりたいと思っている人にはめちゃくちゃおススメです。
6.3.メモ帳は1冊のみで、情報も一元管理する
メモ帳は1冊のみで情報を1元管理するのがおすすめです。
僕も以前はノートを〇〇用とか決めて書いていたのですが、結局取りまとめが大変だったり、ノートがどこにあるのかを探すのが本当に大変でしたのでおすすめしません。
その代わりに、使う一冊は上質なメモ帳を持つことで大切に使え、何か思い出したいときはすぐに見つけることができます。
また、大切なのは書いたノートの内容をクラウド上に保存してどの端末でも見れるようにしておくことです。
情報をクラウド上で保存しておけば、いつでも見返したり、思い出すことができるのでおすすめです。
6.4.4色ペンを普段から活用する
メモを手書きで書くようであれば、4色ペンがおすすめです。
自分の中で色のルールを決めておくことで、4色を使い分けていきます。
慣れてくると、自分のメモを読み返した時に「こんな思い・感情・気づきがあったな」と思いだすことができます。
黒:普段の色
緑:主観的な色、自分の考えなど(0.3㎜)
青:やや重要(0.4㎜)
赤:最重要(覚えるの必須※0.5㎜)
また、何かの記事で読んだのですが、色によってボールペンの太さを変えるようにしています。そうすることで、重要度に対する認識も変えることができたので、おすすめします。
4色ボールペンもずっと使い続けるものなので、普段自分が持っている物よりも少し上質なものを活用しましょう。
僕がこれまで使ってきておススメだったのは「ジェットストリーム4&1ピュアモルト」「クリップオンマルチ2000」「パイロットフリクションボール4」の三つです。
ボールペン一つとってもメモに対する意識が変わりますので妥協しないようにしてくださいね♪
7.メモの取り方を学ぶ「5冊のおすすめ本」
ここまで、メモの取り方と工夫の方法をお伝えしてきました。
最後に、僕がメモを取れるようになるまでに10冊以上の関連本を読んできた中でのおすすめ本を紹介していきます。
メモとは関係ない本もありそうに見えますが、全てメモを取るための重要な観点を学ぶ本になっていますので、必ず読むようにしてください。
全て、完璧なメモを容易に書き、メモを通して実績を出している方々の書籍です。
7.1.超・箇条書き~「10倍速く、魅力的に」伝える技術~
本書は、僕が大変感銘を受けて、今でも読み返すリストに入っているメモの名著です(※僕の中で)
戦略コンサル・シリコンバレーの企業家・MBAホルダーなど世界のエリートは「Bullet Points(ブレットポイント)」と呼ばれる“箇条書き”によるコミュニケーションを大切にしています。
箇条書きは、英語や会計、そしてロジカルシンキングと同じくらい
世界的に求められているスキルなのだ。
というくらい、メモ・箇条書きの重要性と魅力について教えてくれた本です。メモと箇条書きが世界でどれくらい重要視されているか・効果があるか知りたい人におすすめです。
- 箇条書きは海外では必須スキル
- 10倍速く、魅力的に伝わる理由
- 「使えるやつ」かは、箇条書きでわかる
- 「全体像」をつくれば、一瞬で伝わる
- 超・箇条書きで英語もどんどん上達する
7.2.仕事のスピード・質が劇的に上がる すごいメモ。
サントリー「伊右衛門」ほか、様々なヒットCMを生み出した小西利行さんのメモの名著です。
人生を変える14のメモメソッドと題して、本人が使っている具体できなメモ術を惜しみなく教えてくれています。
メモ術が多いので、一度広くメモ術について網羅したい方におススメです。
- 情報をシンプルにまとめ整理する「まとメモ」とは
- クリエイティブ発想を引き出す「つくメモ」とは
- 人に伝えて心を動かす「つたメモ」とは
7.3.[カラー改訂版]頭がよくなる「図解思考」の技術
図解思考も僕の人生を変えてくれた1冊です。
メモというより汎用的な内容になるので3番目に紹介させていただきました。
メモが取れなかった時代に、僕は「話を一度聞いただけで覚える」「メモの取り方が整理されて綺麗」な人の特徴を研究しました。
すると、優秀な人ほど揃って図解思考を取り入れていることが分かりました。その上、図解思考を常に頭の中でイメージしているとのことでした。
図解思考ができるようになると、メモの取り方が圧倒的に変わります。そして情報収集力・整理力・アウトプット力が格段に上がります。
メモを取るだけでなく、総合的な思考力を高めたい人は絶対に読んでほしい一冊です。
7.4.メモの魔力 The Magic of Memos
これは説明するまでもない前田祐二さんの名著ですね。
前田さんの特出した部分は以下2点だと考えています。
- 目の前の物事に対する圧倒的な興味・関心力
- 収集した情報をアウトプットに還元する力
物事に対する興味・関心・疑問がメモを取るためのガソリンです。興味があればあるほど、些細なことでも自分に活かすためにメモを取れるようになります。
また情報収集だけでなく、アウトプットに還元するためにどうすればよいかが分かります。
堀江貴文さんも「前田さんのメモ力は半端ない」というくらいですから、日本一メモを取る人の取り組み内容が気になる人は読むとメモに対する考え方が変わります。
7.5.最短の時間で最大の成果を手に入れる 超効率勉強法
こちらも少しメモからは離れますが、DaiGoさんの超勉強術がめちゃくちゃおススメです。
科学的根拠にもとづいた勉強法について学べる本で、勉強法の考え方がメモの取り方にも活かせます。
数万冊の本を読み、インプットとアウトプットを繰り返すDaiGoさんの思考術を学ぶのは、勉強法を学ぶ上で本当に効率的です。
- やってはいけない勉強法
- 学習効果を高める!「勉強前」7つのテクニック
- 記憶の残り方が変わる「勉強後」5つのテクニック
8.まとめ❘メモの取り方をマスターすると人生が変わる
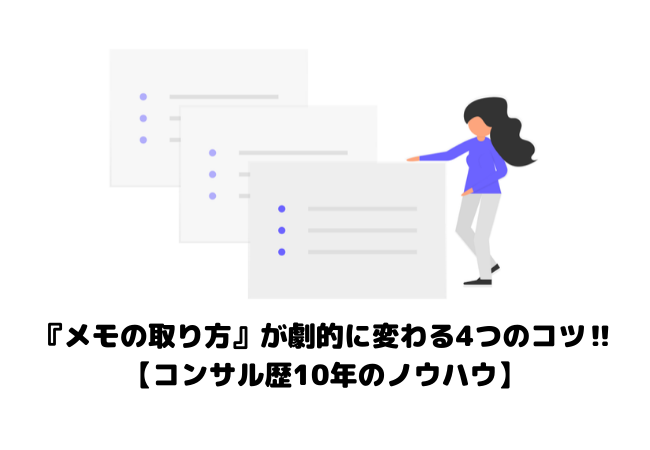
ここまでメモの取り方(基本・練習法・おすすめ本)についてお話していきました。
話をまとめていくと、メモの効果は6つあります。
- 備忘録になる
- 考えをまとめることができる
- アイデアを生み出せる
- 感性が高まり、成長スピードが一気に上がる
- 仕事の成果が出る
- 周囲からの信頼が生まれる
本内容を読めば、必ずメモの取り方が向上することを感じるはずです。
メモは人生を変える重要なスキルです。実際、僕はメモが書けるようになって人生が根本から変わりました。
- 話が整理された状態で頭に入り、ストレスが圧倒的に減る
- 情報を探す時間が減り、振り返りやスムーズに思い出しが可能
- アウトプットやアイデアも生まれやすくなり、会社に価値を提供できるようになる
メモの取り方は教えてもらうこともなく、我流になりやすいので、早い段階でメモの型を身につけて、常に効果的な情報収集とアウトプットができるようにしておきましょう。
この記事を読んでくれた方が、メモの重要性とメモの取り方に気付き、より仕事とプライベートで成果を出せることを心から応援しています!
メモの取り方を学んだところで、次は議事録についても学んでみましょう!
本日は以上です。
本記事を読んだ人が、あわせて読んでいる記事